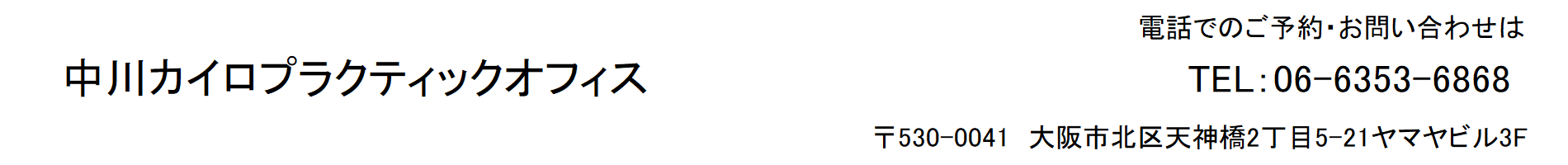当院のカイロプラクティックは、院長が24年間アメリカで学び、アメリカのカイロプラクティック大学で教えた検査法と施術法を使い、皆様の健康を支えます。 当院は、1999年、院長がアメリカから帰国し、これまでホームページも作らず、治療させていただいてきました。しかし、インターネットが一般的になった現在、インターネットを通して来院される方に大きな ご迷惑をおかけすることになってしまいました。そのため、今回少しでも、ご不便を解消して頂きたいと 考え、ホームページを作成することにいたしました。 当院は、痛みがなく、やさしく安全な治療を目指しております
メニュー
● 診療案内
● 院長紹介
● スタッフ紹介
● アクセス
● 治療方針
● カイロプラクティック
● モーション・パルペーション研究会
● 健康ブログ
お知らせ
● 令和5年12月29日(金曜日)から 令和6年1月4日(木曜日)までお休みとさせていただきます
1月5日より通常通りとなります
● 保険は取り扱っておりません